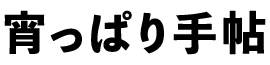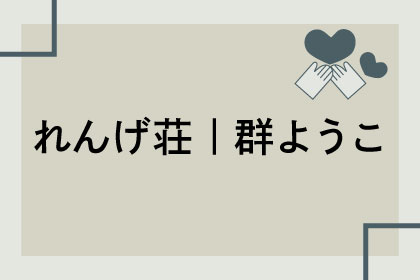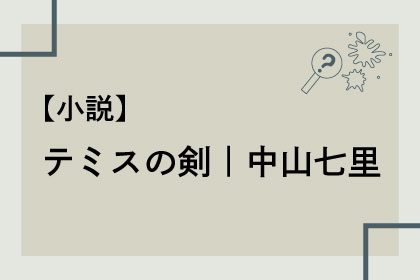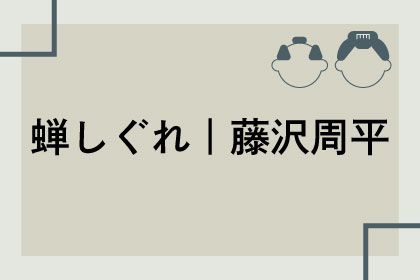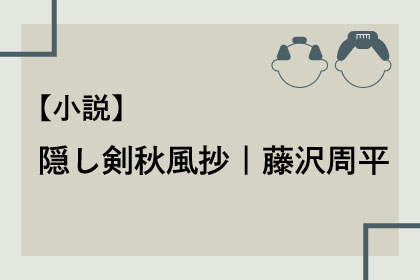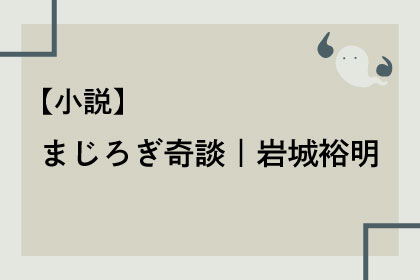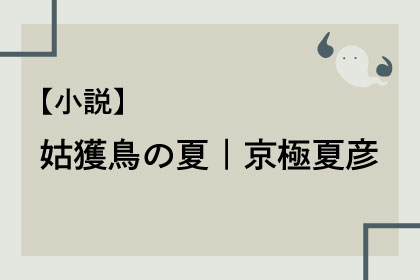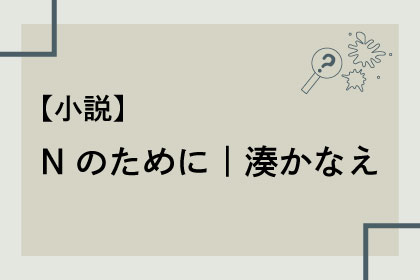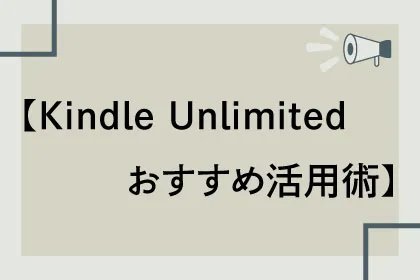【読書感想】神田ごくら町職人ばなし(一)|坂上暁仁|職人魂に心震える漫画でした
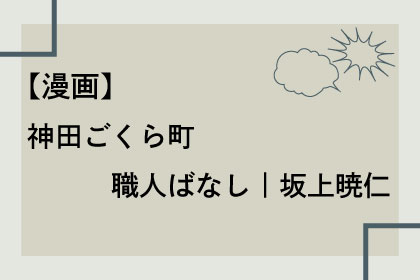
こんにちは、ginkoです。
今回綴るのは、表紙をみかけてずっと気になっていた坂上暁仁さんの漫画「神田ごくら町職人ばなし」。
帯の紹介文から、職人の生き様を描いた物語かと思っていましたが、実際に読んでみると想像以上に「職人たちのモノづくりに対する気概」がひしひしと伝わってくる素晴らしい作品でした。この記事では、本作品の見どころを読書感想とともに紹介するので、気になる人は参考にしてください。
【あらすじ・内容】
江戸にある職人の町「神田ごくら町」。
「職人のとある日常」と題し、次の職人たちを主人公とした話が描かれています。
- 木を大切にする「桶職人」
- 自分の手がけた刀が子ども殺しに使われた「刀鍛冶」
- 流行と藍染の意匠に悩む「紺屋(※)」
- 吉原で畳の張り替えを行う「畳刺し」
- 腕だけでなく頭としての器量も試される「左官」
職人ごとに話が分かれており、基本的には一話完結となっていますが「左官」編のみ3話構成。ごくら町で働く様々な職人たちの技と気概が、圧倒的な画力で丁寧に描かれた漫画です。
※染色をする職人。ここでは藍染色をする職人。
【見どころ・ポイント】
様々な賞を受賞した単行本!!
「神田ごくら町職人ばなし」は以下の通り、様々な受賞や評価を得ています。
- 第28回(2024年)手塚治虫文化賞「新生賞」受賞
- 宝島社「このマンガがすごい!(2024年)」オトコ編第3位
- フリースタイル「THE BEST MANGA 2024 このマンガを読め!」第1位
- 「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2024」第1位
受賞や評価を得られるのは、たとえ一つでもとても素晴らしいことです。2023年9月発売の本作が、第一巻にしてこれだけの評価を集めたというのは、それだけ多くの人に響いた作品であることの証ではないでしょうか。
モノづくりの工程も学べる
この作品では、職人の技はもちろん、モノづくりの工程まで細かく描かれています。桶や刀などがどうやって作られ、何に気を付けているのかを、職人を通してしっかりと伝えているので、感動だけでなく新たな発見も得られる漫画です。
また、それらを漫画として描くには画力だけではなく、十分な知識も必要なはず。時に繊細で、時に迫力のある数々の工程描写は、あたかも自分が経験あるいは見てきたかのようで、まさに圧巻です。
自立した女性が多く描かれている
史実ではどうかわかりませんが、この作品で活躍する職人の多くが女性です。男社会の中で毅然とした態度でモノづくりに打ち込む女性職人は、とてもカッコよく勇気づけられます。
また、頭となった職人が「自分が女だから」と自ら悩む描写は出てきますが、基本的にこの作品で描かれるのは、男も女も関係なく職人としての腕。この時代で活躍できる女性は、実際には少なかったかもしれませんが「いい仕事をするのに性別は関係ない」と思わせてくれる描き方は、現代に通じるものもあって心にとても響きます。
【読書感想】
純粋に人の手だけで作られた製品をみつけたくなった
現代のモノづくりは、機械を使用して大量生産するものが主流。さらには自動化によって生産に携わる人間がどんどん少なくなっている気がします。そんな中「職人」と呼べる方が現代にどれほど残っているのだろうと、この本を読んで思いました。
「コスパ」や「タイパ」が重要視される世の中からみれば、手作りで一つ一つ丁寧に時間をかけてモノをつくるのは、効率も生産性も悪いでしょう。また、そうやって時間をかけて作られた製品は、高値になることが多く、物価高騰と相まって欲しくても手に入らない、入れられない状況があります。
そのため、できるだけ良いものを使いたいのに価格をみて諦めたり、できるだけ安く買うために妥協してしまうことが私にはあります。機械による大量生産が悪いとは思いませんが、読了後は、純粋に人(職人)の手だけで作られた製品を見つけたくなりました。できれば買いたいとも・・・。
また、私自身、イラストや裁縫など、自分で何かをつくるということが好きな性分です。この漫画を読んで、職人の技はもちろん「いいものをつくる」という意地や情熱、執念も感じられて、とても刺激になりました。
今と比べて不便な時代だけど、感覚が優れていたのでは
漫画では、町に住む職人以外の人々も所々に登場しており、職人が仕上げたモノを使ったり、眺めたりする描写が多数出てきます。手や目にしたものが、人を笑顔にさせている描写は素敵で良かったです。
今と違って江戸時代の頃は、全体的に物が少なかったため、道具をはじめ何にしても選択肢がとても限られていました。その分、一つ一つの物や物事に対して集中しやすく、人間のもつ五感がとても優れていたのではないかと思います。
また、わからないことがあっても、今ならネットですぐ調べられるけど、昔は自分より知識のある人に教わるか、自分で考えるしかなかった時代。頭を働かせることが当たり前のようなところもあっただろうから、経験にもとづく知識も豊富で賢こい人が多かったのでは・・・とも思いました。
「左官」の物語が壮大だった
「左官」は3話構成となっており、ごくら町の象徴となっている「蔵(長七蔵)」について、持ち主が「この蔵は100年前に建てられた」と語るところから始まっています。その後、(100年前の)蔵造りの物語が始まるのですが「蔵作りは時間がかかるから話も長いのかな」なんて思いながら読んでいたので、最後の結末を見たときに思わず鳥肌がたちました。
職人の仕掛けた技が見事にプロローグへつながっており、職人の想いも100年後までつながっていたことがとても壮大で良かったです。ちなみに、物語は100年またがっていますが、江戸時代は260年続いていたためか、人や街並みなどの風景に、そこまでの変化は感じられませんでした。
蔵についても、これまで当時の人が何かの保管に建てたもの程度の認識しかもっていなかったため、当時の役割や存在意義を知れたことも良かったです。それを伝える場面での、趣向を凝らした一コマも、漫画でしかできない表し方だなぁと、とても面白くて素敵でした。
単行本の続きはWebで公開されている
「神田ごくら町職人ばなし」は、江戸の様々な職人たちの技や気概をひしひしと感じることのできる物語で、大人の人でも楽しめるオススメ漫画です。手より機械が動くことが多くなってきた現代だからこそ、心に響くものがあるし、今自分が使っているモノをもっと大切にしようと素直に思えました。
もっと他の職人たちの話も読みたいと思い、二巻を探してみたのですが、残念ながら2025年7月時点では、単行本はこの一巻のみのようです。
ただし、本作品はリイド社が運営するWeb漫画サイト「トーチweb」で連載中とあります。このサイトでは、職人たちの新しいエピソードが公開されているので、次の単行本が待てないという人は、こちらをチェックしてみてください。
また、本作以外で大人が楽しめる漫画なら「蝉法師(せみほうし)」もオススメ。蝉の一生を、擬人化した蝉で描くというユニークな内容を、圧倒的画力で力強く描かれています。気になる方は、こちらも参考にしてください。