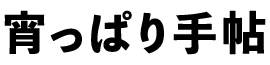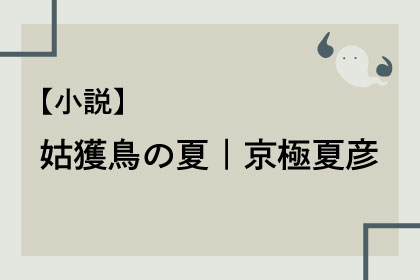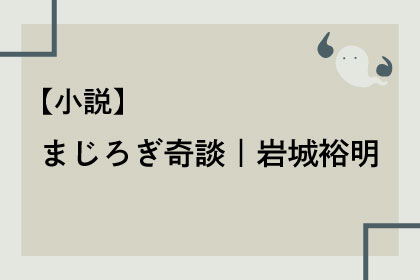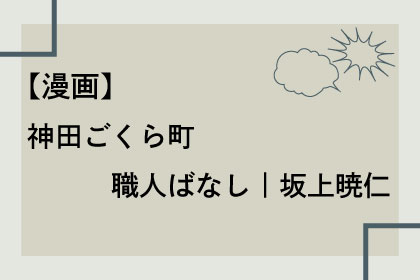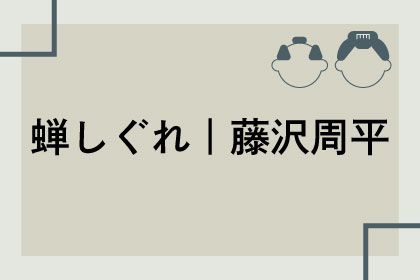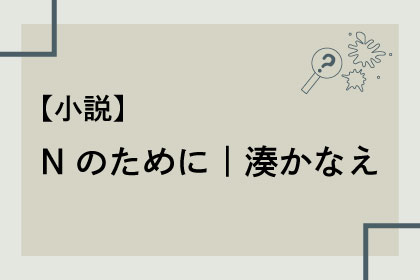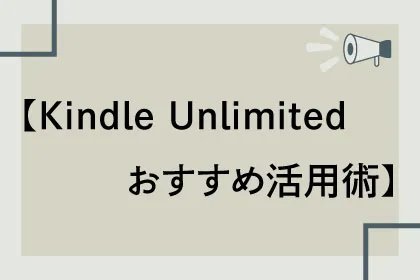【読書感想】テミスの剣|中山七里|冤罪をテーマにした社会派ミステリー
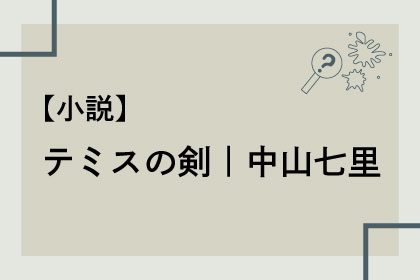
こんにちは、ginkoです。
今回読んだ本は、中山七里さんの「テミスの剣(つるぎ)」。
AmazonのKindle Unlimitedで見つけた本作品は、冤罪をテーマに、一人の刑事が苦悩の中で真実を追い求める姿を描いています。ミステリーとして楽しめるだけでなく、読中読後に考えさせられる要素も多く、なかなか読みごたえのある作品でした。
本記事では、作品の見どころとともに読書感想を綴ります。
【あらすじ】
昭和59年、インター近くのホテル街にある不動産で強盗殺人事件が発生。若手刑事の渡瀬とベテラン刑事の鳴海が捜査にあたり、容疑者として楠木という男が浮上するも、楠木は犯行を認めません。
その後、鳴海による強引な取り調べが続き、疲弊しきった楠木に対し渡瀬が「法廷で否定したらいい」と声をかけ強盗の自白に成功するも、殺人については頑なに否定します。しかし、被害者の血がついたジャンパーが家宅捜査で見つかったと鳴海から告げられ、ついに供述調書にサインする楠木。
続く法廷で、楠木は無罪を主張するも一審で死刑が言い渡され、控訴審においても一審支持の判決(死刑)が言い渡されます。また、楠木は「刑事から暴力によって自供させられた」ことも法廷で訴えましたが、鳴海や渡瀬の否定によって聞き入れてもらえず、そのまま死刑が確定。絶望した楠木は、拘置所内で自ら命を絶ちました。
その後、渡瀬は定年退職した鳴海に代わって堂島とともに、とある強盗殺人の捜査をしていたところ、迫水という人物にたどり着きます。
既視感のある手口に嫌な予感がした渡瀬は、犯行を認めた迫水に対し、不動産での強盗殺人についても尋ねると「それも自分がやった」とまさかの自供。さらに、楠木による殺人の決め手となった被害者の血がついたジャンパーは、鳴海による偽造証拠であることも明らかとなったのです。
取り返しのつかない過ちを起こしてしまったことに、打ちひしがれていく渡瀬。一方、堂島をはじめ警察関係者らは冤罪の隠ぺいに早くも動いており、渡瀬は署内でも孤立していきます。
自分の犯した罪に対して覚悟を決めた渡瀬は、尊敬する検事である恩田に迫水の送検を依頼、楠木が冤罪であったことが世間に明るみとなりました。その結果、事件に関わった警察官、検事、裁判官など多くの人間が処分されることに。
その一方、渡瀬に対する処分はなく、彼は楠木を殺したのは自分だという自責の念と、自分だけ安全圏にいることにやりきれない思いを抱きます。楠木の両親へ謝罪するも当然受け入れてもらえず、それでも事件を忘れることなく「次はもう間違わない」と決意しました。
二十数年後。
警部となっている渡瀬は、無期懲役で服役していたはずの迫水が仮釈放され、その日の内に刺殺されたことを知ります。迫水を恨んでいる人間の仕業であっても、何故、出所したばかりの彼を襲うことができたのか・・・。
蘇る過去の事件につながりがあると考えた渡瀬は、自ら関わった冤罪事件に決着をつけるため、迫水を殺した犯人を突き止めていきます。
【見どころ】
テミスの剣が意味する「力」
テミスの剣とは、ギリシャ神話に出てくるテミス像がもっている剣のこと。テミスは、正義の女神といわれることが多く、善悪を測る天秤と力を意味する剣を持っており、司法における公正さを表す象徴とされてきました。
この作品では警察官、検事、判事など司法権力をもつ人間が多く登場します。「剣なき秤は無力で、秤なき剣は暴力」といわれており、登場人物のもつテミスの剣が果たして公正さを保つ力(権力)なのか、ただの暴力なのかが注目です。
許されざる過ちを犯した渡瀬の贖罪
本作品の大きなテーマである「冤罪事件」。主人公の渡瀬は、この冤罪事件に深く加担しており、一人の人間を自殺にまで追い込んでしまいました。どれだけ悔んでも、大切な命が戻ってくることはありません。
取り返しのつかない過ちを犯してしまった時に、その過ちとどう向き合っていくのか。作中では、渡瀬の心の葛藤が丁寧に描かれており、彼は出口のない答えの中でもがき続けます。覚悟を決めた渡瀬が、どんな目にあっても逃げずに真実を追い求めていく様はスリリングであり、深く感銘を受けるでしょう。
リアリティ感じる司法組織の闇
「何故冤罪事件が起きてしまったのか」
本作品では、組織のメンツや保身のために真実が捻じ曲げられていく様だけでなく、裁判で一審判決を覆すことの困難さも描かれています。警察や検察、裁判所の闇がリアルで、現代社会における司法制度への問題提起としても機能しているのではないでしょうか。
冤罪事件において、個人がどれほど無力で組織がいかに真実を阻害するかが見どころであり、考えさせられるポイントでもあります。
【読書感想】
※ここからはネタバレが含まれています。
読後に残ったのは爽快感ではなく重みだった
読後にまず思ったのが「重い」でした。
司法とは、正義とは、殺人とは、裁かれるとは・・・・など、読中に出てくる「問い」が後を絶たず、とにかく考えさせられる部分が多かったです。登場人物によっては、その人なりの思考や答えがわかるものもありましたが、結局のところ、その答えは読者にゆだねられている気がします。
冤罪をテーマにしているとはじめからわかっていたので、重厚なストーリーになると想像していましたが、ここまで重いとは思いませんでした。
なかでも「無実を訴えても一審(死刑)が覆ることはないのに、人を殺して無期懲役と判決されても服役中の態度で仮釈放に覆る」という内容は、初めて知ったと同時にかなり衝撃でした。司法に関してド素人で無知な自分ですら「何で???」と感じましたし、特に冤罪被害に遭われた人や家族が納得できないのもうなずけます。
その一方で、組織における問題については共感する部分もありました。こういった問題は、どの分野においても起こりうる話で、自分自身も嫌な経験があります。結局のところ、司法に携わるものも「人間」である以上、起こりうるのかなとも思いますが、やはりあってはいけないでしょう。
話自体は、ミステリー要素も当然多く、判明する事実や展開を存分に楽しめましたが、読後は要所要所の問題が余韻となって残りました。
渡瀬の「逃げない」姿に感銘を受けた
渡瀬は、冤罪事件の加担者となってしまい、取り返しのつかない過ちに苦悶し続けます。前情報から、この人(渡瀬)が冤罪に加担するんだろうなと思って読んでいたため、冤罪発覚後に彼がどうするのか、どう変わるのかに注目していました。
結果、渡瀬がキレイごとのようではなく、むしろ泥臭い感じに描かれていたのが良かったです。彼は、大切な命を奪ってしまったことだけでなく、真実を明らかにすることの意味にも悩み苦しみます。渡瀬の犯した罪は、個人の問題ではなく組織の問題でもあるため、罪に真正面から向き合う(真実を明らかにして正す)ことの難しさも考えさせられました。
渡瀬の悩みに悩む姿は非常にリアルで人間味にあふれており、特に冤罪事件後は、ことあるごとに深く考える描写が多く出てきます。迷いながらも彼の「逃げない」姿や「もう間違えない」という決意、危険を顧みずに真実を追い求める執念に、とても心が打たれました。
個人的には彼の上司であった鳴海も何かしらの報いを受ける、あるいは少しでも反省して欲しかったと思いましたが・・・。
人を裁くのは司法機関だけではない
法治国家の日本において、法を犯した人間を裁くのは司法機関です。それ故に、証拠を捏造したり、直接手を下さず間接的に加担するなどして「法で裁けない悪事を働く人間もいる」という事を、改めて思い知らされました。
その一方で、法律による罰を受けなくても、世間への広まりで好奇の目に晒され、バッシング、解雇、左遷など社会的な制裁を受ける人間も少なからずいます。作中において、その「法で裁けない悪事を行った人間」を社会的に「裁いた」のが、司法機関と何の関係もない一般人(マスコミ)であったことにも感慨深いものがありました。
特に最近は、SNSが浸透しており、一般人の声による影響が大きな時代になったと感じます。見方を変えれば、一般人が社会的な冤罪を生み出してしまう可能性も多いにあるということ。だからこそ、自分の発する声、言葉に責任を持たなければならないと改めて思いました。
「テミスの剣」の続編も気になる
中山七里さんの「テミスの剣」は、一つの冤罪事件を軸に、司法機関における闇が浮き彫りとなった重厚な社会派ミステリーです。重いテーマではありましたが、飽きのこない展開で一気に読み進めることができ、最後まで楽しむことができました。
この作品には続編があるそうで、本作品で真実をより執念深く追い求めるようになった渡瀬が、その後どう活躍するのかが気になるところです。機会があればそちらも読んでみたいなと思います。