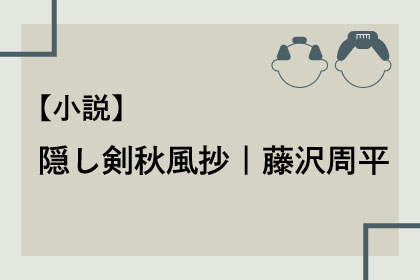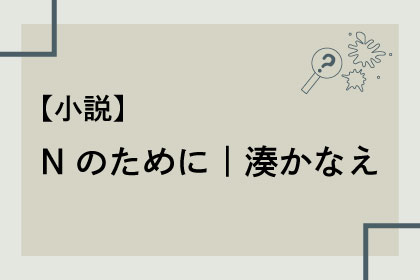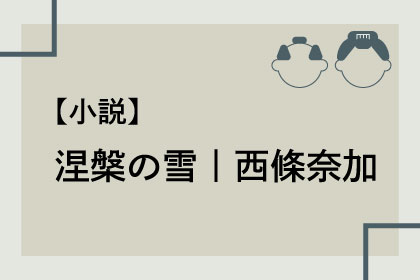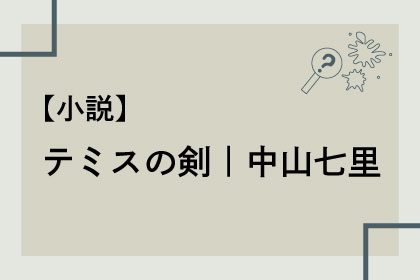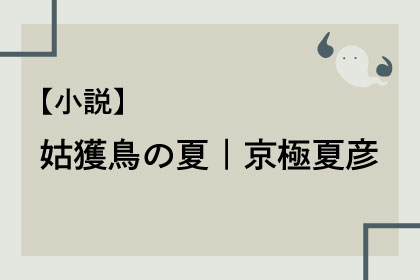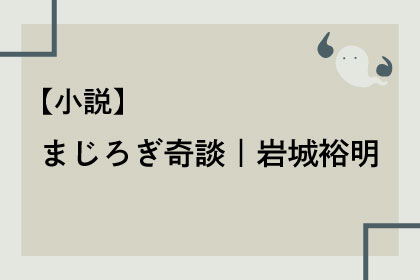【読書感想】一茶|藤沢周平|頭の中の上品なイメージが完全に覆されました
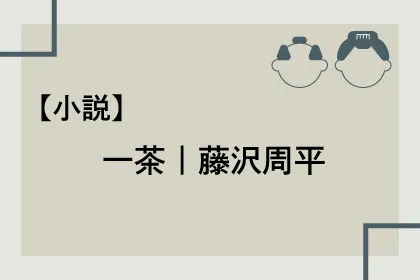
こんにちはginkoです。
今回は藤沢周平さんの作品「一茶」について、読書感想を綴ります。
本作品は、俳人「小林一茶」の生涯を描いた、伝記小説です。私は小林一茶について、正直名前は知っているけど、俳句を読んでいた人みたいな印象しかありませんでした。恥ずかしながらどんな句を読んでいたかも存じません。
また、藤沢周平さんの作品は好きでよく読むのですが、こういう著名な方を題材にした小説も書いていたんだという興味もあり、読んでみることにしました。
結果、面白かったかそうでなかったかと言えば、面白くはなかったのですが、それは「小林一茶=有名な偉人=名声を手に入れた人」みたいな勝手なイメージを膨らましていたため。史実に基づいた物語となっているため、面白いと感じる要素というより「そうだったんだ」という驚きと発見に満ちた読了となりました。
個人的に感じた見どころも合わせて紹介するため、本作品が気になっている人は参考にしてください。
【一茶の内容】
15歳の弥太郎は父の弥五兵衛に見送られ、生まれ育った信州の柏原から江戸の奉公に出向くところから物語は始まります。父は本当のところ、弥太郎を江戸に行かせたくなかったのですが、弥太郎と継母さつの関係があまりにも悪く、致し方なく二人を引き離したのです。
この弥太郎が、後の「一茶」。
弥太郎は、江戸でも上手くやれずに奉公先を点々とします。その中で偶然知った御法度の遊び「句合わせの会」を覚え、その縁で俳諧師と名乗る露光と知り合いました。
露光の世話によって俳諧を学びながら働いていた弥太郎は、やがて俳諧師「一茶」として独立します。しかし、俳諧師として食べていくのは至難の業。
弥太郎は、常に貧困との隣り合わせで、家族愛にも飢えていましたが、その中で浮かぶ句を次々と作っていきます。その数、生涯で2万句。
貧しさ、家庭内確執、世の中への恨み、孤独・・・負のスパイラルの中で膝を抱えて耐えながらも生への執着で65歳まで生きぬいた小林一茶の生涯がこの小説に凝縮されています。
【小林一茶ってどんな人物?】
小林一茶は、松尾芭蕉や与謝蕪村と並び江戸時代で活躍した俳諧師です。本作を読むにあたり、小林一茶について少し調べてみました。
※尚、江戸時代は長く、松尾芭蕉は一茶が生まれる前に活躍しており、本小説では一茶が芭蕉にならって旅に出るという描写が出てきます。
【小林一茶の代表句】
小林一茶は生涯で2万もの句を詠んだといわれておりますが、中でも次の句が代表句のようによく挙げられています。
- めでたさも中位なりおらが春
- 雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る
- 是(これ)がまあ 終(つい)の栖(すみか)か 雪五尺
解釈は所説ありますが「春(正月)のめでたさは自分にはこの程度」「(雀に対して)早くどかないと馬にひかれる」「五尺の雪に埋もれたこの家が自分の最後の住処」といった内容の句で、一茶には感じたことをストレートに表現する独特のスタイルがあります。
【小林一茶の生涯】
本名は弥太郎といい、1763年に長野県北部にある柏原宿(現信濃町)の農家に生まれました。3歳のときに母が亡くなり、8歳で継母を迎えますがうまく馴染めなかったため、15歳の頃に江戸へ奉公に出されます。
江戸では奉公先を点々とし、20歳を過ぎたあたりから俳句の道をめざすようになったとか。葛飾派三世の溝口素丸、二六庵小林竹阿、今日庵森田元夢らに師事して俳句を学んだ後、一茶という俳号を用いるようになったといわれています。
その後、30歳前後で信州への帰郷や、関西や四国、九州への俳句旅などをしており、その間に句集などの出版もしています。40歳くらいの時に父が他界しますが、父が書いた遺言(田畑や家屋敷を弟と半分ずつ分けるという内容)をきっかけに、継母・弟との遺産争いがその後10年以上にわたって繰り広げられました。
争いがようやく決着して信州に帰ってきた後、52歳で初めての結婚をします。しかし、せっかく恵まれた4人の子供はいずれも幼いうちに亡くなっており、さらには妻も若くして亡くなるという不幸に見舞われました。
再び一人になった一茶はその後2度結婚しましたが、その間火事によって母屋を失い、焼き残った土蔵での生活の中、65歳の若さで生涯を閉じたといわれています。
【一茶のみどころ】
小林一茶のイメージを覆される
小林一茶のことを「なんとなく知っている」程度であれば、おそらく私のように「俳諧師=風流・おだやか・上品」みたいなイメージをもっている人は多いのではないでしょうか。あの独特な僧侶のような装束で優雅に句を詠んで人に称賛されていたかのような。。。
そのような印象をもっていたならば、そのイメージは完全に覆されてしまいます。
作中の一茶は、残念ながら風流とはほど遠く、世を渡るために表面上のおだやかさを演じているだけの、拗ねた人物。ただし、心は弱く、常に何かに傷ついていたり不安や焦りの毎日の中、孤独な人生を送った人物でもあります。
その背景には、幼いころからの継母との確執や信州生まれ(田舎者)に対する軽蔑などがあり、一茶が生きるために必死にもがいていたこともわかるでしょう。
一茶が作った句の背景がみえてくる
もちろん全部ではありませんが、作中に一茶の作った句も多数登場します。一茶はその時に感じたことをそのまま句にしているため、その内容はとてもストレート。
時には自嘲めいていたり、世の中を皮肉っていたり、中には「こわい句をつくりましたな」と先輩俳諧師に心配された句も出てきます。句が生まれた背景がみえるため「だからこの句を詠んだんだ」とより深く理解することができるでしょう。
藤沢周平さんの描く小林一茶
藤沢周平さんは、歴史小説が好きな人なら知らない人はいないくらいの有名作家です。本作品は、フィクションではなく、史実に基づいた物語となっているため、他の作品でみられるようなストーリー性はありません。
しかし、藤沢さんならではの緻密な描写は本作でも健在で、どれだけ下調べをしたんだろうというくらいの再現性を感じます。一茶の人物像だけでなく自然描写も圧巻で、読んでいるとその情景が次々と頭に浮かんでくるでしょう。
個人的には、一茶が生涯を閉じるところで潔く「完」となっているところが良かったです(笑)。
読書感想
ここからは「一茶」を読了して感じたことを綴ります。
一茶だけでなく俳諧師というものも学べた
「俳句は5・7・5で言葉を紡ぐ句」みたいなことしか知らない自分にとっては「そもそも俳諧師って何?俳句を詠む人のこと?」と思いながら読み進めていたので、勉強になるようなことばかりでした。句合わせから歌仙(かせん)といった「俳諧」に関するものが多数登場し、江戸時代にそのようなものが流行っていたことにも驚きました。
その俳諧のプロのようなものが俳諧師ですが、それだけでは生活ができないため、多くの俳諧師は本業をもっていたそうです。一茶はそれでも俳諧師一本で生きていたため、常に貧困に苦しんでいましたが、旅先で食住を支えてくれた人の存在があり、今の時代との違いも感じました。
また、俳諧には様々な流派があるだけでなく、地方によっても傾向が異なるというのもびっくりしました。一茶も当初、ある派閥に属していましたが、途中で抜けており、最後まで独自のスタイルを貫いていたため、存命中はかなり稀有な俳諧師だったのではないでしょうか。
切なすぎる人生
史実を調べていると、一茶は存命中にすでに有名になっていたような説もありましたが、本作では「名は通るようになったけど、他の俳諧師に比べて負けている」ような状態でした。そのため、一茶は俳諧師としての成功(多くの人に認められているという意味での)を感じることが出来ないまま生涯を終えていたのが、とても切なかったです。
小林一茶という人物は実際に存在した人で、教科書にのる、そして小説にもなる、いわゆる「後世に名を残した」人物。しかし、当の本人は生涯お金や家庭愛などに飢え続け、ようやく感じた幸せの感情も束の間に終わっています。
人物像については作者の想像も含まれていると思いますが、判明している史実からみても一茶はかなり苦労していると思います。作中のように悲哀に満ちた人生だったのかなと思うと、後世ではなく生きているうちに何かしらの揺るぎない幸せを掴んで欲しかったなと思いました。
切ないけども・・・
何度もいいますが、私は小林一茶をよく知らないまま読んたので、彼や彼の作った句を知ることができたのが今回の読書における収穫です。作中に登場する句はあまりにもストレートすぎて、中には「こんな句詠んでいたの?」と面白いものも多々ありました。
例えば「春立や四十三年人の飯」「はつ雪やといえば直二三四尺(二はカタカナ表記)」など、自分を自嘲したり、風流ぶいた句への反発でつくったもの。なんとなく言いたいことがわかるくらいのストレートさで、本人は辛い事の最中なんだろうけど、こじれ具合がもろに出ていて少し笑ってしまいました。
「一茶」は小林一茶の人となりが知れる名作だった
本作は小林一茶の史実に基づいており、そしてその生き様があまりにも切なすぎるため、読了後はスッキリとした気持ちになりませんでした。しかし、藤沢周平さんの匠な描写によって、一茶のことや彼の詠んだ句について深く知ることができて良かったと思います。
今回は史実ベースでしたが、藤沢周平さんの作品には他にも名作がたくさんあります。別の記事では『蝉しぐれ』や『隠し剣秋風抄』についての感想を綴っているので興味のある方は参考にしてください。
最後まで読んで下さり、ありがとうございました。